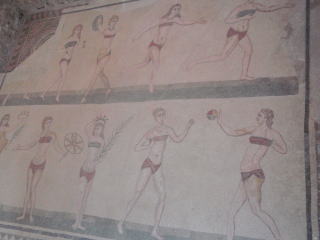| 42期 徒然草 | |||||||||||||||||
| シチリア島を訪ねて | 阿保 文敏 | ||||||||||||||||
「シチリア島」はイタリア半島の南部、つま先に隣接して浮かぶ、地中海最大の島そして地中海の真ん中に位置する。本土とはメッシーナ海峡を船で40分程、列車を運ぶ連絡線がある。 シチリアに興味を持ったのは、ローマ帝国の初期、カルタゴとの戦い(第1次ポエニ戦争)の場となった処を見たいと思ってのことだ。ついでに南イタリヤをナポリ~アルベロベッロと観光した 〔州都パレルモ〕が最初の訪問地 人口68万 古くから続く大きな町で商工業 観光交通の要点となっている。 地中海の真ん中に位置する温暖な地、その故にギリシャ、ローマ、アラブ、ノルマンと南北からの支配を重ねており、異文化の入り混じった独特の雰囲気を漂わせている。
観光パンフの中にノルマン王宮とあるがノルマン王宮とは何だと疑問に感じた。ノルマンはバイキングの南下勢力の末裔が起こした王朝となっている。南イタリヤの豪族の内紛に際して、北フランスからノルマンの傭兵を雇い入れたが雇い主の豪族が共倒れになり、その隙に傭兵隊長がシチリヤを制圧したようで面白い。ナポリを含み半島南部を制圧 ギリシャへも勢力拡大を図るも達成せず。
〔島の東海岸に多い別荘地のひとつタオリミーナ〕 海岸線から急な崖の上にコンパクトな町が乗っかって居る。 崖の上の町からは、はるか遠くにエトナ山、眼下に青いイオニア海を眺望に収め、さわやかな風が吹き抜ける最高のリゾート地。
島の東部はエトナ山(3323mの活火山)がそびえ、独立峰の裾野が緩やかに広がる 活火山で時々噴火を繰り返す。 地形は丘陵地が発達所々に渓谷、果樹が多く、葡萄も特産でワインが有名。 島の西部は丘陵地帯、高い山もなく、畑地が広がる。 今回の旅ではシチリアに5月末の4日間滞在。 もっとゆっくりシチリアを楽しみたい気分、田舎のゆったりした風情が残っている。 ナポリ~アルベルベッロは又の機会に |
|||||||||||||||||