| 42期 徒然草 | |
| 読書のすすめ(15) | 小栁 毫向 |
今回は、まずノンフィクションを2冊紹介します。 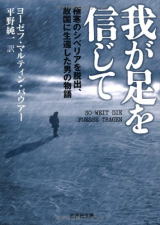 1冊目は、ヨーゼフ・マルティン・バウアーの「我が足を信じて」(文芸社文庫960円) 第2次大戦でソ連の捕虜となったドイツ軍人がシベリアの東の果て、ベーリング海を挟んでその向こうがアラスカというまさに極東の捕虜収容所に入れられ、鉛の掘削をやらされていたが、その収容所を脱出、故国ドイツに帰還するまでの9,000マイル(14,400キロ)3年2カ月に及ぶ脱出行を小説化したもの。 世界で3,000万部売れているというから大ベストセラーといってもいいでしょう。 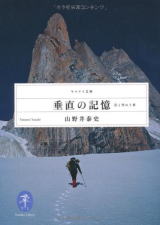 2冊目は山野井泰史の「垂直の記憶」(山と渓谷社880円) 2冊目は山野井泰史の「垂直の記憶」(山と渓谷社880円)山野井は、以前紹介した沢木耕太郎の「凍」のモデルとなったクライマーであり、酸素ボンベなしに単独もしくは極少数で登るアルパイン型の世界有数の登山家である。 その彼がこれまで挑戦した垂直の壁、時にオーバーハングした壁に挑んだ記録である。 最後の7章に「凍」の舞台となったギャチュン・カン北壁が紹介されているが、彼はこの挑戦で手と足併せて10本の指を凍傷で失くしたが、それでも壁に挑戦する夢を持ち続けている。 この2冊を読むと、人間の生命力の凄さを感じさせてくれる。 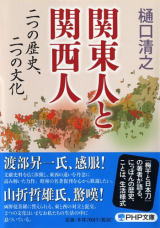 もう1冊、なるほど、なるほどと思いながら読める本を紹介します。 樋口清之の「関東人と関西人」(PHP文庫700円) 樋口は「梅干しと日本刀」で結構知られた、日本人とは何ぞや、を追求する学者である。 皆さん、東京を中心とする周辺を関東といわれるのは何故かご存知ですか。 もともと日本の都は奈良・京都でその都を守るため伊勢の鈴鹿,美濃の不破、越前の愛発(あらち)に関所が設けられその東を関東と言っていたが、江戸時代になり箱根の関が重要となりその東いわゆる関八州が関東といわれるようになったそうです。 東西の文化の違いをいろいろな面から説明してくれます。まさになるほどザワールドの世界です。 |
|