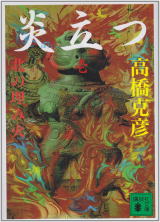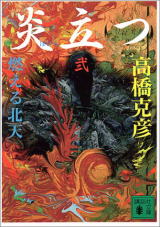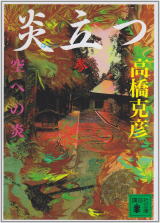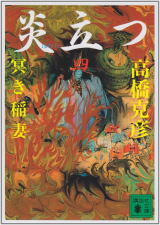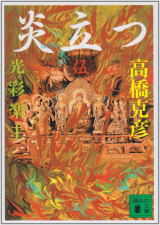| 42期 徒然草 | ||||||
| 読書のすすめ(22) | 小栁 毫向 | |||||
しばらくのご無沙汰でした。 今回お勧めするのは、加藤陽子著「それでも、日本人は戦争を選んだ」〈新潮文庫〉 著者は東大の教授で近現代史を専門とする。 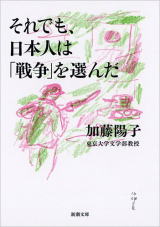 日ごろ東大の学生に近現代史を教えているが、大学生に近現代史を教えるのは遅いのでは、という疑問を持ちある中学と高校の歴史に興味を持つ生徒に5回にわたり教えたものを収録したものがこの本である。 日ごろ東大の学生に近現代史を教えているが、大学生に近現代史を教えるのは遅いのでは、という疑問を持ちある中学と高校の歴史に興味を持つ生徒に5回にわたり教えたものを収録したものがこの本である。採り上げた戦争は、日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦、満州事変と日中戦争、太平洋戦争。 それぞれの戦争に至った要因を分析し、なぜ日本人が戦争を選んだのか、あるいは選ばざるを得なかったのか、をわかりやすく解説している。 我々がかって学んだ戦史は戦闘戦史が主体であったが戦争という大きな概念で学ぶことのほうがより重要ではないか。 お孫さんから戦争の質問を受けたときこの本はいい参考書になる。 もう一つ、高橋克彦著「炎立つ」(講談社文庫全5巻) 以前同じ著者の「火怨」を紹介したと思いますが、「火怨」は坂上田村磨呂とアテルイとの戦いの物語。 「炎立つ」はその250年後安部一族と源頼義・義家の戦いに始まり、その後いろいろな経緯を経て藤原王朝が成立し、そして藤原王朝が滅びるまでの歴史を描いた物語である。
私はかって平泉の中尊寺を見学したことがある。そのとき藤原というのは土着の氏なのか、それとも京の藤原と関係があるのか疑問に思っていましたが、この本が明快な回答をしてくれました。 初代藤原泰衡には安部一族と京の藤原の血が流れていました。 藤原王朝は最盛期白河以北を有する大帝国でした。 藤原三代といわれますが、正確には四代目の泰衡の時に源頼朝が襲い掛かる、このとき藤原王朝は15万の精強な騎馬軍団を擁しており、頼朝と十分に渡り合えたと思われますが、このとき泰衡のとった行動は、15万の騎馬軍団を解体し、平泉をきれいに清掃して無抵抗で明け渡し、自らは切腹して首をはねさせ、その首を頼朝に差し出した。 なぜこのような行動をとったのか、泰衡の考えは300年以上前のアテルイの考えとと同じでした。 十分に戦えるがその戦いの中で民に塗炭の苦しみを与えてしまう、これを避けたかったそして何よりも蝦夷と言われた国の末永い安寧を祈ったから。 中尊寺は世界遺産に指定された。誰よりも清衡が喜んでいるような気がする。 |
||||||