| 42期 徒然草 | ||||
| 行く末(3/3) | 谷口 日出男 | |||
介護用語は、実際その世界と接触ない限り、潤いのない難解な言葉が多い。「小規模多機能型居宅介護」なんて言われてもなんのこっちゃ?と初めて耳にする人は想像もつかないだろう。そんな介護施設の用語に「認知症対応型共同生活介護」というのがある。通称「グループホーム」っていうやつである。所謂、昔でいう「老人ボケ」今は訂正?されて「認知症」。その認知症老人たちの収容施設である。ご存知のように、少人数での共同生活をしながら、家庭的な雰囲気のもと、入浴、排せつ、食事等の日常生活が送れるようにとお世話する施設である。家族からの要望や多角的に?患者や利用者を取り込もうとするわが病院もこの施設を2年前に立ち上げた。そして何の因果か今年になって、そこの管理も任された。今までの管理者が去ってしまい、そこに充てるべき人間がまだ見つからんのである。 この種の職務、経験や資格や研修とやたらと肩書き?が要る。その施設の立ち上げに全面的に関わり、一朝、事ある場合を思い、これまであれこれ取っていた資格や研修がここに至って、本人の意思に拘わらずに役立ってしまったのである。今まで医療や介護の場に身を置いてたとはいえ、ノホホンと外野席のアルプススタンドで応援者の気分で、みんなの仕事振りを眺めていた身分から、日々、お年寄りの状態を確認し、そんなお年寄りを介護する職員の苦労を共に肌で感じ、彼女たちのボヤキを直截聞かされるグランドに引きずり降ろされた。 医は算術の感覚?の管理者のもと(これはこれで100人もの職員を抱える経営者の理念としては正常である)で、自分の置かれた立場上、その職務を投げ出すわけにもいかず、この年になって天罰が下った思いのもと、生き物?相手のこの職務、盆正月もない勤務体制にとドップリとハマってしまっている。あ~ぁ!
"あのー、一万円足りないんですけど" "そうけぇ、揃えて持ってきたつもりじゃけど" 改めて二人でその紙幣を数える。やっぱり一枚、足りなかった。持ってきた財布を広げるも、もう万札は、残ってないようだ。 "あっ、不足分は、今度来られるときにでもいいですよ" "いやっ、どっかにあるはずだ"と財布の中身を全部、カウンターの上に、引っ張り出す。カードの間から、四角にきれいにたたまれた万札が出てきた。それを広げて渡された。長い間、大事にたたまれていたのかきれいな織り目がついている。先月の施設の利用料とオムツ代として合わせて12万7643円が不足なく揃い、支払わされた。領収証を切って渡す。彼は、支払いに来るときは、いつも仕事帰りなのか、やや汚れた工員服を着て、夕方7時過ぎに、玄関に用意したスリッパは、履かずに支払いに来る。入居者の息子さんで、年は50の後半か、五分刈りの頭にはもう白いものが目立ってきている。ここの利用料、振り込みにしてるんだけどこの田舎では、ほとんどがこうして現金で支払いに見えられる。支払日が来るのは早く、先月払ったかと思ったらもう今月の支払いに来なきゃならんと、そんなグチを聞きながら、申し訳なく?利用料等を頂いている。毎月。12万円余の支払い、大変だろうな。こうして、毎月この金額を揃えなければならないその苦労が察せられる。聞けば、この入居者、夫の遺族年金があるわけでもなく、またこの時代の人たち、自分が受け取る国民年金は微々たるものである。ほとんどがこの息子がやりくり算段して毎月揃えているようだ。 介護保険等の施策で至れり尽くせり?の老後の世界になったけど、こうして年老いても金がかかる時代になったのだ。これから先、世の中の状況が激変し、今の年金制度でも破たんしたり、老人の世話をどこで見るかが問題になった時に、果たしてどうなるんだろうと不図思う。 "○○さんは元気ですよ、今夜も全部ご飯を食べられて、今はもう休んでおられますけど、どうぞ部屋でも覗いて行ってください"と言っても"うん、いいわ、行ってもわからんし、よろしゅー頼んどきますわ"と言って、支払いだけ済ませ、帰られた。 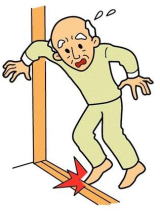 ○○さん、94歳になるおばあちゃんである。要介護度5、ベッドからの寝起きも、車椅子での移動も、食事介助もそして排泄介助もすべて全面的に職員の手助けがないとできない。おまけに話す言葉もゼロでこちらからの問いかけにも9割がた理解できてないのか反応がない。つまり、お互いのコミュニケーションは、全然取れないのである。こんな状態なれど、ヒトは生きているんである。だが、息子が言うようにもう、何にもわからん状態である。ただ、今のところはどこと言って体には悪いところはないし、おまけに食欲は、旺盛だし、入れた分だけ、定時にはちゃんと排泄している。これから先もこの状態が続いていくだろう。ここの施設での最長老は、101歳のおばあちゃんだけど、優にそこまでは到達しそうな感じである。ただ、頭の方は、すでに壊れ?自分で意思を表示できないし、相手の言うことも理解できない。認知症の究極のひとつのタイプがここにある。こんな状態の母親を見る息子の心境は、彼とのやり取りであれこれと察することができる。"もう、十二分に生きてきたし、ここいらでシマエテよかろうもん"と息子としては思うも、現実にはそういうわけにもいかんしなぁとシミジミと繰り言を言う。そうだろうな、そういうわけにもいかんだろうなぁ・・・これが少しばかり言葉でもやり取りができ、ひ孫でもなつくようなおばあちゃんなら見舞いに訪れる励みにもなるんだがこうもなると訪れる人も少なくなってくる。 ○○さん、94歳になるおばあちゃんである。要介護度5、ベッドからの寝起きも、車椅子での移動も、食事介助もそして排泄介助もすべて全面的に職員の手助けがないとできない。おまけに話す言葉もゼロでこちらからの問いかけにも9割がた理解できてないのか反応がない。つまり、お互いのコミュニケーションは、全然取れないのである。こんな状態なれど、ヒトは生きているんである。だが、息子が言うようにもう、何にもわからん状態である。ただ、今のところはどこと言って体には悪いところはないし、おまけに食欲は、旺盛だし、入れた分だけ、定時にはちゃんと排泄している。これから先もこの状態が続いていくだろう。ここの施設での最長老は、101歳のおばあちゃんだけど、優にそこまでは到達しそうな感じである。ただ、頭の方は、すでに壊れ?自分で意思を表示できないし、相手の言うことも理解できない。認知症の究極のひとつのタイプがここにある。こんな状態の母親を見る息子の心境は、彼とのやり取りであれこれと察することができる。"もう、十二分に生きてきたし、ここいらでシマエテよかろうもん"と息子としては思うも、現実にはそういうわけにもいかんしなぁとシミジミと繰り言を言う。そうだろうな、そういうわけにもいかんだろうなぁ・・・これが少しばかり言葉でもやり取りができ、ひ孫でもなつくようなおばあちゃんなら見舞いに訪れる励みにもなるんだがこうもなると訪れる人も少なくなってくる。そして、年老いても、こうして本人の意思に関係なく、わが子に金銭的迷惑をかけている。 先般の統計によれば、全国で認知症患者は、462万に達し、65歳以上3,079万人のうち、その15%を占めているとか、すでにもう、七人のうち一人が認知症なのである。60代、70代では、認知症になる率は少ないが、これが85歳以上になれば、もう40%に達っしているとか、これから老人が増え、その老人が長生きし、80の後半から90代も優に生き延びていけば、もうこれはゆゆしき問題なのである。新聞記事によれば、すでに認知症と判定される者の他に、その予備軍と言われる「軽度認知症(MCI)」と呼ばれるグループがなんと、約400万人も控えているとか、しかし、何もこの400万人がすべて認知症になるわけでもないだろう。こんな統計上の予想数字、どこまで受け取っていいかわからん時がある。ただこの老人認知症、一旦かかれば治る見込みのない症状である。  認知症、厄介である。内臓疾患やどっかの骨がおかしいの、腰が痛いのなんていうのは、その症状がわかりその対応策も良いか悪いかは別にしても目に見えている。ところが認知症に至っては、見た目にはどこといって悪いとこはないんだが物事の理解ができなく、自分が何しているかわからんのでその対応に苦慮する。もう、自分の力だけでは、正常な日常生活、社会生活を送れないのである。なんでこんなに多くなったんだろう。 昔は、おじいちゃんというのは、いつも背筋をシャキッと伸ばし、威厳があり、時折孫に訓示を垂れ、おばあちゃんはいつもあちこちと動き回って仕事をし、孫の顔を見れば、満面の笑みを浮かべて愛しんでくれたものと相場が決まっていたもんだが、今はもう、その尊厳もなくただ反応なしに生きてるだけの年寄りが目立つ。医療介護の世界に身を置き、日々そんな人ばかり見ているせいもあるだろうが、ボケ老人なんて小さい頃、周りに居たかなぁ・・・それだけ、人間が長生きし、その年寄りの生きる環境が変遷しているのだろう。 いつか信州長野を旅したときに、松本から長野行の列車に乗った。列車が山間(やまあい)を通っていく。駅に着いた。窓の外に善光寺平の街並みが見下ろされる。絶景である。スイッチバックの案内が出ていた。駅の名は、「姥捨駅」だった。へーぇ、こんな駅名があるんだ。その時、ここが「楢山節考」の舞台だったのかと思った。 品のいい入居者の老婦人が言う。"ここは現代版、姥捨て山ですね"と。当を得ているが捨てているのではない。どこも行くとこがないお年寄りをここでは、拾っているのであると言ってもその老婦人は、このギャグは理解できんだろうな・・・こんな風に、姥捨て山なんて言葉を発し、見た目には正常な老婦人だけどやることなすことピントがずれる。子供たちが帰って来るからご馳走を造らなきゃと、夜中に起きてきて騒いだり、トイレと風呂場を間違えて汚したりとあれこれと職員の手を煩わす。見かけは穏やかでまともなんである。ところがある時、特に夜中なんかに異常をきたす。とてもじゃないが毎晩、こんな状態が続けば在宅での家族の面倒見は、限界に近づいてくるのである。自分を育み、愛してくれた親、その親の老後は、今度は自分が恩返ししたい。しかし、日々働き、生活している家族にそれが出来なくなったのである。 なんで? それは、お互いにその為さざるところに、そのもとがあるんだろう。こうして、親をこんな施設に預けるのは、当事者でなければ理解できない苦渋の?決断なのである。そう言う俺だって、おふくろをこのように、施設に預けている。そしてその面倒見は、近くにいる兄弟にオンブダッコして貰い、数か月に一回ぐらいしか見舞いには行っていない。大きなことは言えないのである。 そんな思いをしながら、施設に入っている親を見舞うために訪れる家族を見ている。この人たちにもそれぞれの思いがあるんだろうと・・・そして、この認知症が抱えるこれから先の爆弾を思うと他人事じゃない。俺達も老夫婦、二人っきりの生活、どっちかがこうなったらそこは、もう地獄?である。でもこればっかしは、避けて通りたいところだが、本人はなりたくなくてもそうなってしまうんだろうか・・・ こんな悲観的な話を女房にしたら"そん時は、そん時だわ、いまごろから、あれこれ悔やんでいてもしようがないわ"と云う。女性の方が長生きする要因は、ここにもあるか...  川井君の終活(今回、シューカツなんて言葉があるのをはじめて知った)についての卓見を読んだが、とてもじゃないが俺にはそんな理性ある?行動は取れっこない。イジイジと生きることにしがみついているだろうなぁ、しかし、この歳でこうして日々、ボケゆく老人を見ていればそうもなりたくない。俺の望むところは、サッカー試合でのゴールを決めた瞬間のポックリ死が仲間から拒絶されたいまは、適当な老年期に、里帰りをした子供たちが朝食時に、"おじいちゃん、いつまで寝てんだろうね、きのうのゴルフとゆうべの焼酎呑みで疲れたのかな?誰かちょっと見てきて"でその終焉を知ってもらうのが一番なんだけどなぁ・・・ そんなの無理か・・・ |
||||