| 42期 徒然草 | ||||
| 母子(おやこ) | 谷口 日出男 | |||
初めて、女性を部下に持った。三人もである。 しかしそのうちのひとりは、自分が上番して数日後には、三人目の出産のために産休に入った。そして、自分は、その職務を一年の短さで下番した。その間、産休にはいった女性職員に対しては、自分から何の声掛けもしなく、在職中に一度、彼女が三人目の子供さんを抱いて職場を訪れた時になんかありきたりのお祝い事だけを言っただけだった その当時、産休の職員が新しい上司に対し、どんな気持ちを抱いていようかと思いも及ばなかった。 一言の思いやりの言葉も発することができない余裕のない管理者だった。そして、それから何年後、娘が結婚し、子供が生まれ、彼女も同じように働くママさん自衛官となった。
今夜は何を作ろうかな、子供もこの時間おなかすかしているだろうけど自分も昼間の陸上戦闘訓練でおなかすいたなぁ。これから料理を作って子供に食べさせて、終わったらすぐに後片付け、それからお風呂に洗濯と続く「おさんどん」、しんどいなぁ・・・ 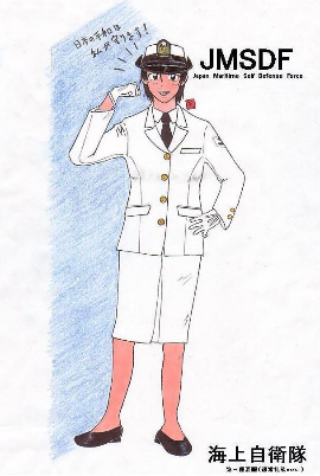 しかし今夜は、違った。車から降りて見上げる家の窓からは暖かそうな明かりが、そして玄関の扉を開けるとおいしそうな匂いが漂ってきた。 しかし今夜は、違った。車から降りて見上げる家の窓からは暖かそうな明かりが、そして玄関の扉を開けるとおいしそうな匂いが漂ってきた。子供は、大きな元気な声で"ただいま!おばあちゃん"と靴もおっぽり出して飛びついていった。母が福岡から広島の呉まで陣中見舞いに来てくれたのだ。小さなちゃぶ台に女三代、楽しいそして母手作りの料理がいっぱい並んだおいしい夕餉である。 いつも料理の出来上がるのが待ちくたびれてソファーで眠ってしまう娘も今夜は、幼心を絞ってあらん限りの努力でちゃぶ台の話題を独り占めしようとしている。二代の親は、それをやさしく聞いてあげた。涙が出そうなしあわせを感じた。 同じ海上自衛官で艦艇勤務のため不在の多い夫は、今は遠くインド洋に給油支援に行ってもう三ヶ月になる。帰ってくるのはまだ二ヶ月先だ。 いつもの母と娘の侘びしい母子家庭の日々が繰り返される。仕事が終わるとすぐに職場を飛び出し、保育園に子供を迎えに急ぐ。晩秋から冬に掛けてはすぐに日が暮れ、保育園に到着するころは、もう真っ暗である。 この時間帯、まだ引き取り手のない子供はそう多くは残っていない。子供も朝七時すぎには預けられ、それから十一時間も集団生活に揉まれてきた。疲れるでしょうね・・・ "お部屋で待ってたら"の保母さんの声にも耳を貸さずぼんやりとした明かりの玄関口で、今夜も両足を揃えてチョコンと座って迎えの到着を待ちわびていた。 "ごめんなさいね、遅くなって" 満面の笑顔で迎えてくれる子供をしっかりと愛情で抱きしめ、夜の道を我が家に向かう。月に数度の当直で契約の里親に預けたり、熱があっても朝早く起こして病児保育に預けたりと子供のことを思えば何度、仕事を辞めようと思ったことか、だけど辞めずに頑張ってきた。海上自衛官として与えられる仕事には、日々満足感があり、張り合いが沸いてくる。そして苦労があればそれだけ幸せがご褒美として戻ってくるかもしれない。 何よりも自分で選んだ道、これからも頑張っていこうと思う。 ◆ そしてリタイア後、二度目の職場は、女の職場とも言える病院勤務となった。ここで沢山の働くお母さんとしての女性を初めてつぶさに見た。  一家の主婦として、母親としての女性の苦労とその母と子のこまやかな愛情のやりとりが良くわかる。 朝方、母親と離れたくなくてぐずついた子供を保育園に預けるのが少し遅れたんだろう、駐車場から走って職場に向かっている。また時折、夕方行われる院内勉強会では最後に質問しようものならどことなく鋭い?視線を感じる。皆、一刻も早く帰って子供の待つ家に帰って、夕餉の支度をしなきゃならんのだ。 そんな時に暇人(ひまじん)がダラダラと質問して・・・。 そして時折、夕方子供が待合室で宿題のノートを拡げて勉強している。看護婦の母親が仕事を終わるのをそこで勉強しながら、待っているのである。 母親が仕事を終えて一緒に帰る子供の顔は、得意げな満面の笑みである。働く母親は誇りであるが、子供はみんな母親大好きでいっときもそばを離れたくないのである。 自分の娘が子供を持ち、働くお母さんとして冒頭のような気持ちで頑張っている姿を見、また年老いた患者に毎日、優しく接している看護婦さんたちの姿を見るにつけ、現役の頃は関心も持たなかった彼女たち外で働くお母さんの裏側の苦労を垣間見た。 そして母と子の愛情の深さを知り、そして何よりもそんなことはおくびにも出さずに職場で頑張っている彼女らを知った。 俺たちの時代は、結婚したら幹部の妻は仕事を辞めて専業主婦として生きていくのが当時の慣例?だった。今の時代には考えられない感覚だったかもしれない。 我が家も当然そうなった。そして日本各地を流浪しながら、妻が専業主婦として三人の子供を育ててくれた。感謝している。 しかし時代は変わったのである。外で働くお母さんが増えたのだ。
自転車の前に一才くらい、後ろに三才くらいの幼児を乗せ、背筋をシャキッと伸ばした制服姿の婦人自衛官を。 まだ朝の七時ちょっと過ぎたばかりである。自衛官の朝は早い。それにしてもこの母親、何時に子供を起こしてこうして今の時間帯、自転車に乗せてんだろう。 自分もさることながら、子供たちにもちゃんと朝ごはん食べさせたんだろうか? モッコリと着ぶくれした自転車の前の子は、冷たい風をまともに受け、目を細めながらもしっかりと前を見つめているが、後ろのお兄ちゃんは、母親の背中に顔をくっつけて寝ていた。  朝、この三人乗りの自転車姿のママさん自衛官を見るにつけ、あれこれと連鎖的に頭の中をいろんな思いと反省が駆け巡る。WAVEとして頑張っている自分の娘のこと、日々こうして今の職場で感じているお母さん女性の元気に働く姿を・・・頑張ってるよなぁ、母親も子も・・・ 朝、この三人乗りの自転車姿のママさん自衛官を見るにつけ、あれこれと連鎖的に頭の中をいろんな思いと反省が駆け巡る。WAVEとして頑張っている自分の娘のこと、日々こうして今の職場で感じているお母さん女性の元気に働く姿を・・・頑張ってるよなぁ、母親も子も・・・そして現役の頃、管理者として女性職員への思いやりがいまいち足りなかった自分を省みる。 聞けば、陸上自衛隊も駐屯地内に保育所が開設されるとか、自分たちの頃にはなかった男の思惑?を超えた時代が到来しているようである。 現役諸官のご苦労を思う。 ヒトが何よりの骨幹戦力である自衛隊の集団、そのヒトを生み、育てる母親達(何もそれは母親だけのものではないが・・・)は、この少子化の時代に仕事に育児にと健気に頑張っている。そしてその子供たちも・・・ (P.S.) この拙文は、本年三月号「修親」で女性自衛官特集記事が組まれた時に、その記事の末席に連ねたものである。 我々現役の頃は、婦人自衛官と言っていたが今は女性自衛官と言う。その女性自衛官の数は、現在、約一万二千人、全自衛官約二十二万五千人の約五%に相当する。 また女性事務官等は約5千人、全事務官約二万一千人の二十四%を占めているそうだ。 平成もやがて三〇年が近づくいま、自衛隊もまた様変わりしていく。某国のWAC部隊の行進風景を見てると、これから時代を経るにつれ、わが陸上自衛隊の女性部隊もまた精強であって貰いたい。ガンバレ!女性自衛官! 蛇足ながらその修親記事にあの山崎宇宙飛行士の寄稿文が載っていた。父君はBの3期生で、官舎が真駒内時代に、官舎のみんなで寒い中、雪だるまやかまくらを作り、母が作った豚汁を食べながら見上げた星空の綺麗さが原体験の風景だったそうだ。 うちの子供たちも同じようにその真駒内で星空を見たんだろうけど、末娘が宇宙じゃなくて大海原の方に行った。 
|
||||