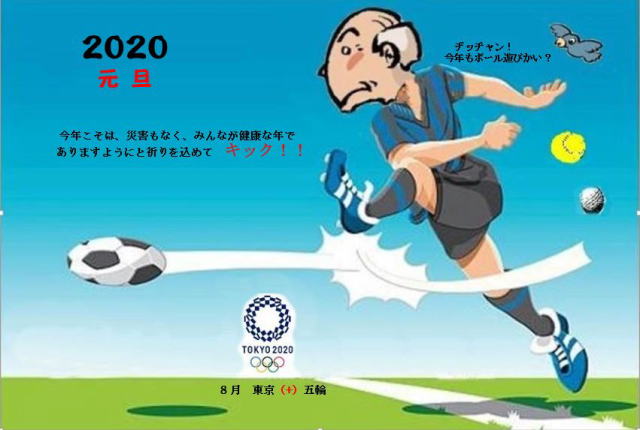| 42期 徒然草 | |||||||||||||||
| 素直なじいさん | 谷口 日出男 | ||||||||||||||
バスの中は、すでに学生で混んでいた。 街の方であるゴルフ仲間の新年会に出席するため久し振りにバスを利用した。夕方の五時過ぎ、丁度下校時間である。 このバスの始発場所に私立の学園があるので乗っているのはそこの生徒さんだろう。 女学生の多い中、男子生徒も何人か乗っている。 バスカードを読み取り部に当て中ほどに進む。するとすでに椅子に座っていた制服姿の男の子がサッと立った。 そして俺の顔を見て、頭をチョコッと下げて声には出さないが"どうぞ!"の仕草をした。
まぁよしんばその男の子が俺に譲った席と感じたとしても俺の躊躇さが"あっ、このじいさん座らないんだ"と自分勝手に解釈し、席を盗った?のかも知れない。 もちろんオバハンはその男の子に礼を言うわけでもない。 いずれにしろ彼が折角俺に譲ってくれた席はオバハンに占領された。 その間、俺はなにも彼にお礼の言葉を発する反応も出来なかった。 彼の好意がオバハンに行ったとしてもそれは彼の本意でないだろう。 本来なら図のようになるところ俺の一瞬のたじろいが彼の好意を無為にしたのだ。 バスは、途中更にお客さんを乗せた。今度は大学生の集団である。 バスの中がますます混んできた。 若者誰もがあのリュックを背負っているので余計バスの中、窮屈感がある。 俺は背中に足の長い若者の気配を感じながら先程の男の子の真後ろで吊革に掴まっている。 こんなに混んだバスに乗るのも珍しい。もうすでに40名近くも乗っているのに話声ひとつも聞こえてこない。 大学生や高校生が多いんでもっとおしゃべりなんかで騒々しいかと思ったが意外と静かである。 驚くことに席に座って居るものは大半がスマホを弄くっている。立っている大学生たちも立ったままスマホを弄くっている。片手だけでメール打っているのもいる。器用なもんだ。
新聞かなんかに、近頃の若者は、席を譲らないという記事が載っていた。 その中で約6割の者が席を譲っても断られた経験があるそうだ。 そんな時は心が傷つき、余計なことをしなければ良かったと自己嫌悪に陥ったと述べている。
そんな思いで先ほどその申し出を素直に受けなかった自分に忸怩たる思いがした。 目の前に立っている孫と同じ世代の彼になんとお礼の言葉を云うべきだったかあれこれと思い巡らす。 その優しさに何か返答してやらなきゃいかんだろう。しかしもう言いそびれてしまったなぁ・・・ それも然りながら自分が席を譲られたことに "そうか、もうそんなお年寄りに見えてしまうんだ" と現実を思い知らされた。 孫たちから"おじいちゃん"と云われても、全然抵抗感もないけど、孫たちと同じ世代とはいえ、他人?からそう扱われると愕然と来る。 そうだよなぁ、若い人から見れば、顔は黒いももう頭は真っ白だし、自分でまだまだと思っていてもその容貌、服装、動作、臭い?からは完全に年寄りに見えるんだろう。 とうとう彼に何も言い出せないままバスは、目的地の停留所に着いた。 そこは電車への乗り継ぎ場所で大半のお客さんが降り始めた。彼はそこでは降りないんだろう、降りる人の邪魔にならないよう通路を開けた。 降りる乗客の流れる中、彼の前に来た。 言った "ゴメンね!さっきはどうもありがとう!" と小さく声を掛けた。一瞬、オッと驚いたような仕草で俺を見た。 彼の顔に笑みがいっぱい溢れた。小さくお辞儀を返してくれた。 何も言わなかったが彼のその笑みと仕草から、"あっ、このおじいさん、自分が席を譲ってやったことがわかっていてくれていたんだ" と彼は思ったと確信した。 自分の気持ちが彼に伝わったことで何かホッとするものを感じた。 降りてバスを見るとその男の子と目が合った。 俺がやぁ!と手を上げ、お礼のため頭を下げると、優しい目をした彼がニコッと笑みを浮かべ小さく手を振ってくれた。 彼にもおじいさんがいるんだろう、俺のことをどんなおじいさんと見てくれたんだろうか、彼から見られることを意識して背筋を伸ばして歩いた。 飲み会の場所へと歩く道すがら、降りる時に思い切って彼に声を掛けて上げて良かったなぁという自己満足感?とバスの中から男の子ながら、じいさんにこうして小さく手を振ってくれた彼の優しさと育ちの良さに、得も言われぬ満足感を感じた。 多分その子と60歳以上の年の開きがあるだろうがそれを通り越して相通ずるものがあることに幸せを感じた。 彼も家に帰ったら、今日のことをどんなにして母親に話すんだろうか・・・ 自分の年を感じさせられた現実があるものの若者との心温まる秘かな?交流が心を豊かにしてくれた。 しかしまぁ、こんなことを感じること自体が年老いた証左なんだろう・・・ 新年会の場でこの話をしてみようかな? 年寄りの仲間内の飲み会なんでまた相通ずるものを持ったひとがいるだろう。 素直なとしよりであることの大切さを・・・
|
|||||||||||||||