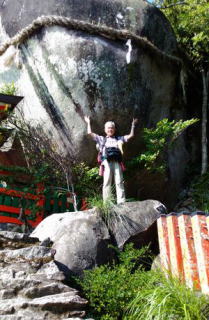| 42期 徒然草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊野古道・小辺路歩き旅 | 山田 和夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒例の夏の歩き旅は、最近の5年間は富士五湖をめぐる旅だったが、今年は年齢、体力を考えてテント泊から民宿に代えて、熊野古道の歩き旅を実施した。 8年前に無事に四国お遍路でやり遂げたお礼参りとして高野山の総本山・金剛峰寺をお参りして、そのまま熊野古道を歩く。 熊野古道は、紀伊半島南部の熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)へと通じる参詣道のことで、昔から皇室、貴族、庶民などのあらゆる階層の人々が詣でた。 今回は、いくつかある参詣道のうち、高野山と熊野本宮大社とを結ぶ小辺路(こへじ)を3泊4日で歩く。 出発直前に、台風12号が東から西へ逆走する異例のコースを辿って、三重県伊勢市付近に上陸して近畿地方に大きな被害を与えたので、予め民宿に電話で状況を確認したところあまり雨は降らなかったとのことなので計画通りに出発した。
歩いている時はもっと暑く、500㏄のペットボトル3本では足らず、脱水気味になってふくらはぎや太腿が痙攣を起こして難儀した。 高野山山門は高野山の総門で、開創当時は現在地より下にあったそうで、現在の建物は1705年に再建され、両脇の運長作の金剛力士像は奈良東大寺の仁王像に次ぐ大きさで、とてもダイナミックで迫力満点だ。 宗教都市・高野山は、標高800メートル、道路沿い約1.5キロメートルにわたって多くの寺院が立ち並び、その先が奥の院になっている。 奥の院に近い宿坊・赤松院(せきしょういん)に泊まったが、出てきた坊さんは来日して15年の若いアメリカ人だった。平日だったこともあり観光客は少なかったが、町で会う人はほとんどが外国人でまるで外国に来ているような感じだった。 赤松院は寺院ではあるが実態は旅館のようなもので、少年野球に参加する韓国の子供たちで食事も風呂も大混雑だった。 高野町には3~4カ所に野球場があり、例年この時期は野球大会で宿坊が占領されるそうだ。久し振りで子供たちと風呂で大騒ぎしたのが楽しかった
北条政子が夫・源頼朝のために建立した金剛三昧院の脇の急坂を上り、薄(すすき)峠~水ケ峰~平辻など標高約600m~1,100mの古道を上り下りする。 本来の古道の雰囲気を色濃く残した小砂利が露出した道が続く。木蔭を進み気持ちが良いが、小石を踏むと転倒する危険があるので決して気を抜くことができない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感想 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ テント泊から民宿に切り替えることで体力の衰えをカバーして、今年も歩き旅を実施した。 段々をぴょんぴょんと飛び跳ねるように下りることは無理で、杖を突きながら一歩一歩確認しながらの状態で、脚力の衰えを実感した。 終わってみて、よく無事に歩いたなぁと感慨ひとしおである。 7日間の歩行記録 歩数:22万歩 距離:162キロメートル 消費カロリー:9,000キロカロリー ・ 現代の四国お遍路や熊野古道は、多くは自動車道路に拡幅されてしまい古来の姿はほとんど失われている。 四国のお遍路では8~9割が舗装道路になっていたが、今回の小辺路では山中の経路がほとんどで往時の姿をとどめている。昔の人々がこの道を参詣路とし、通商などの生活路として利用していたことは、いかに脚力が優れていたか改めて認識した。 40代から糖尿病で苦しみインシュリンを1日に4回も打っていたのが、お遍路を終えてからは朝夕の錠剤に代わった。 その後毎年夏に1週間~10日ぐらいの歩き旅を続けていることで、いまだに悪化せずに済んでいるのだから、歩き旅は今後も続けていきたいと思う。 ・ 携帯電話も通じない山中で利用した2件の民宿は、いずれも80代と思われる老婆が経営し、同居の家族は両家とも50代と思われる息子ひとりだけだった。 他人ごとではあるが、民宿の跡を継ぐ人はないと思われ、過疎の村の実態を垣間見た気がする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||